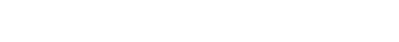2025年6月、職場における熱中症対策の義務化がスタートします。これまで努力義務であった熱中症予防措置が、一定の条件下では「法的義務」として明記されることとなり、事業者や労務管理者にはより一層の対応が求められることになります。
この記事では、法改正の背景・具体的な義務内容・対象範囲・罰則規定に加えて、労務担当者が実務で講じるべき対応策をわかりやすく整理しました。
■ なぜ法改正が行われたのか:背景と目的
日本の夏季における気温上昇は年々深刻化しており、職場での熱中症による労災も増加傾向にあります。特に屋外での作業や高温環境下での業務では、労働者の健康被害や生産性の低下が懸念されてきました。
厚生労働省はこの状況を踏まえ、2025年6月から**「職場における熱中症予防の強化措置」**を義務化することを決定。これは労働安全衛生法に基づく省令の一部改正として公布され、事業者が熱中症の予防体制を整備しなければならない法的根拠が明確化されます。
■ 改正内容のポイント
2025年6月以降、以下の条件を満たす場合には、事業者による熱中症対策が義務となります。
◯ 対象となる作業条件
- 暑さ指数(WBGT)が28℃以上
- または気温が31℃以上
- かつ、1日4時間超または1時間以上継続する作業
◯ 義務となる主な措置
- 作業環境の把握
- WBGT計による定期的な測定(推奨頻度:1日数回)
- 測定結果の記録・保存
- 労働者の健康状態の把握
- 熱中症の既往歴や健康情報の事前聴取
- 異常のある作業者の把握と対応体制
- 緊急対応体制の整備
- 連絡網や搬送先の明確化
- 医療機関との連携体制
- 教育・訓練の実施
- 熱中症の兆候、初期対応、予防策などを含む教育
- 休憩・水分補給の確保
- 定期的な休憩時間の設定
- 冷房・送風設備の整備
- 十分な飲料の供給
- 記録と管理
- 対策の実施記録の保存(指導・教育記録、WBGT記録など)
■ 労務担当者が取るべき実務対応
制度施行に向けて、労務・総務部門には以下のような実務対応が求められます。
① 対象作業・対象者の把握
まず、自社の作業環境が**「WBGT28℃以上」「気温31℃以上」「4時間超」**に該当するかどうかを確認しましょう。特に以下のような業務は対象となりやすいため注意が必要です。
- 建設・土木・運送などの屋外作業
- 製造業で高温の炉・装置のある現場
- 空調のない倉庫内作業
- 運転業務(配送、建機など)
また、高齢者・肥満・持病持ち・暑熱順化が不十分な新入社員など、ハイリスク者のリストアップも行いましょう。
② WBGT測定器の導入・測定体制の整備
今後、WBGTの定期測定が必要になる可能性があるため、以下を準備します。
- 測定器の購入(1万円〜数万円程度)
- 測定場所の選定(作業場所、代表点)
- 測定結果の記録・保管(帳票 or デジタル記録)
特に**夏季繁忙期前(6月まで)**には、測定体制を整備しておくことが望まれます。
③ 社内規程・マニュアルの見直し
熱中症対策を衛生管理体制の中に組み込むことが重要です。
- 「熱中症予防規程」の策定
- 衛生委員会での定期報告・議題化
- 「異常時の対応マニュアル」作成
- 休憩時間の再設計(熱中症リスクに応じて増加)
可能であれば、衛生管理者・産業医と連携して、実効性あるマニュアルを構築しましょう。
④ 教育・訓練の実施
教育訓練は年1回以上を基本とし、以下の内容を含めるのが推奨されます。
- 熱中症の初期症状と重症化サイン
- 予防策(服装、水分補給、休憩など)
- 万一のときの初期対応(冷却、搬送)
動画教材やeラーニングを活用すれば、多拠点企業でも効率的に教育が可能です。
⑤ 外部専門家の活用(産業医・衛生管理者)
社内での対応に限界がある場合、外部の産業医・労働衛生コンサルタントの活用が現実的です。
- 衛生講話での教育提供
- ハイリスク者の就業可否判定
- 環境測定・改善提案
費用はかかりますが、労災防止・リスク対策という観点からは投資対効果が高い施策です。
■ 対応を怠った場合のリスク
今回の法改正では、明確に**「事業者の義務」として規定**されており、違反時には以下のようなリスクがあります。
- 是正勧告・指導
- 労働基準監督署による行政処分
- 労災認定時の企業責任の増加
- 社会的信用の失墜・報道リスク
2025年の夏以降は、「熱中症が発生=企業の管理義務違反」とみなされる可能性が高まるため、早めの対応が求められます。
■ まとめ:法改正を「チャンス」に変える
今回の熱中症対策義務化は、ただの規制強化ではなく、労働者の安全確保を企業価値向上に繋げるチャンスでもあります。
- 労働者の健康被害の防止
- 離職・労災リスクの低下
- 生産性の維持・向上
- 働きやすい職場づくり(健康経営)
これを機に、組織としての安全文化の醸成にも取り組み、持続可能な労務管理体制を目指していきましょう。